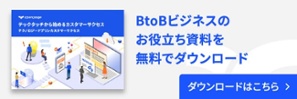自治体向けの営業とは、民間企業の営業活動とは本質的に異なるアプローチが求められる特殊な領域です。多くの企業が「自治体の課題を把握する」ことから始めようとしますが、実はこれには大きな落とし穴があります。本コラムでは、自治体営業の真の出発点である「課題意識を作ってくる」という視点から、効果的なアプローチ方法を考察します。
自治体職員の現実:なぜ「課題把握」では不十分なのか
多くの企業が自治体営業で失敗する理由は、最初から「課題を教えてください」というアプローチを取ってしまうことにあります。しかし、自治体職員の置かれている環境を理解すれば、なぜこのアプローチが効果的でないかが見えてきます。
日々の業務に忙殺される職員
自治体職員の多くは、日々の業務に忙殺されています。住民サービスの提供、法令に基づく事務処理、議会対応、予算管理など、その業務は多岐にわたり、常に時間に追われている状況です。さらに、3年程度での人事異動により、ようやく業務に慣れた頃には別の部署へ異動となり、また一から新しい業務を覚えなければならないという構造的な問題も抱えています。
このような環境下で職員から聞こえてくる「課題」は、往々にして「忙しいから楽にしたい」という主観的なものになりがちです。しかし、これは本当に解決すべき課題なのでしょうか。
客観的視点を補う必要がある
忙しさに追われる職員にとって、自らの業務を俯瞰的に見つめ、客観的に課題を分析する余裕はほとんどありません。また、外部の最新情報やベストプラクティスに触れる機会も限られています。結果として、他の自治体の事例を表面的に真似するか、前例踏襲に終始することが多くなってしまいます。
これは職員の能力不足ではなく、構造的な問題です。だからこそ、営業側が「課題意識を醸成する」という役割を担う必要があるのです。
課題意識を醸成する3つのステップ
自治体職員に本質的な課題意識を持ってもらうためには、段階的なアプローチが不可欠です。いきなりヒアリングから始めるのではなく、まず職員自身に「気づき」を与える体験を提供することから始めましょう。
1. 実証実験:前例主義の壁を越える第一歩
自治体は本質的に前例主義的な組織です。新しい取り組みには慎重にならざるを得ず、「他でやっていないこと」への抵抗感は強いものがあります。しかし、実証実験(PoC)という形であれば、「期間限定」「地域限定」という条件付きで新しい試みを受け入れやすくなります。
実証実験の真の価値は、単に新技術の効果を検証することだけではありません。職員自身が実際に体験することで、「こんなことができるのか」「これなら業務が変わるかもしれない」という気づきを得られることにあります。つまり、実証実験は課題意識を醸成するための強力なツールなのです。
実証実験設計のポイント:
- 期間は2〜3ヶ月に設定し、明確な終了時期を示す
- 対象範囲を限定し、リスクを最小化する
- 定量的な評価指標を事前に設定する
- 週次での進捗確認と調整を行う
- 実際に使用する職員を巻き込んだ体験型の検証を実施
勉強会:組織全体の理解度を高める
個人レベルでの気づきだけでは、組織は動きません。ある研修で「役立ち度は高いが活用度は低い」という結果が出た際、その理由は「上司や同僚が同じ知識を持っていないため、理解してもらえない」というものでした。
だからこそ、勉強会という形で組織全体の理解度を高めることが重要です。
効果的な勉強会の設
- 自治体の実情に即した内容:一般論ではなく、その自治体特有の課題や事例を用いる
- 階層を超えた参加:担当者だけでなく、管理職も含めた幅広い参加を実現する
- 継続的な実施:単発ではなく、シリーズ化して理解を深める
- 双方向のコミュニケーション:講義形式ではなく、質疑応答や討論を重視する
- 他自治体事例の共有:成功事例だけでなく、失敗事例からの学びも提供する
3. ヒアリング:対話を通じた課題の言語化
実証実験と勉強会を経て、ようやく本質的なヒアリングが可能になります。この段階でのヒアリングは、単なる情報収集ではありません。職員と一緒に課題を言語化し、整理していく共同作業です。
効果的なヒアリングのポイント:
- 「何かお困りごとはありませんか?」という漠然とした質問は避ける
- 具体的な業務プロセスに沿って、詳細に聞き取る
- 他自治体の事例を交えながら、比較の視点を提供する
- 現在→過去→未来の順で、段階的に深掘りする
- 職員自身の言葉で課題を整理してもらう
- 解決の優先順位を一緒に考える
実証実験から始める:短期間で成果を可視化する方法
実証実験は単なる「お試し」ではなく、本格導入への戦略的な第一歩として位置づけることが重要です。適切に設計された実証実験は、当年度内の予算化・導入も可能にします。
なぜ実証実験が突破口になるのか
自治体営業において、「当年度中の予算化も可能」という事実は意外と知られていません。実は、適切なタイミングで実証実験を開始し、明確な成果を示すことができれば、補正予算での対応や既存予算の組み替えによって、年度内での本格導入も十分可能なのです。
成功のポイント:
- スピード感のある実証実験設計
- 実証期間を2〜3ヶ月に設定
- 4〜6月に開始すれば、8月頃には成果データを取得可能
- 9月の補正予算編成時期に間に合わせる
- 明確な評価指標の設定
- 業務時間の削減率(例:書類処理時間を50%削減)
- コスト削減効果(例:年間100万円相当の人件費削減)
- 住民満足度の向上(例:窓口待ち時間を30%短縮)
- 実証実験中の巻き込み
- 現場職員だけでなく、管理職や財政部門も早期から参画
- 実際に体験してもらうことで、効果を実感として理解
- 「これは使える」という確信を組織全体で共有
勉強会の本当の価値:組織全体の理解度を高める
勉強会は単なる情報提供の場ではありません。組織全体の意識を変革し、課題解決への共通認識を形成する重要な機会です。
勉強会がもたらす組織的な変化
知識の共有化: 個人の学びを組織の資産に変換することで、属人的な知識に依存しない体制を構築できます。特に人事異動の多い自治体では、知識の継承は重要な課題です。
意思決定の質向上: 管理職も含めた幅広い層が同じ知識基盤を持つことで、より的確で迅速な意思決定が可能になります。
変革への抵抗感軽減: 新しい取り組みへの理解が深まることで、変革に対する不安や抵抗感が軽減されます。
継続的な学習環境の構築
効果的な勉強会は単発で終わらず、継続的な学習環境を構築します。月次や四半期ごとの定期開催により、知識のアップデートと組織の成長を促進します。
まとめ:真のパートナーシップの構築
自治体営業は、単に製品やサービスを売り込む活動ではありません。職員と共に課題を発見し、解決への道筋を示す「課題意識の醸成」こそが、その本質的な役割です。
実証実験、勉強会、ヒアリングという3つのステップを通じて、職員自身が気づいていなかった課題を可視化し、客観的な視点から解決策を検討する。このプロセスを丁寧に進めることで、自治体と企業の真のパートナーシップが生まれ、住民サービスの向上という共通の目標に向かって進むことができるのです。
忙しさに追われる職員の主観的な「楽にしたい」という声の奥にある、本質的な課題は何か。それを一緒に見つけ出し、解決への道を示すことが、これからの自治体営業に求められる姿勢ではないでしょうか。
この記事を書いた人
|
openpage 事業開発部長 北森雅雄(kitamori masao) NTT東日本で14年間、自治体SE、新規事業開発、デジタルマーケティングを経験し、総額10億円の案件創出や年間ARR10億円規模の事業立ち上げを実現。2025年にopenpageに転職し、現在は事業開発部長として8がけ社会時代の営業DX推進に取り組む。 |
 |
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら