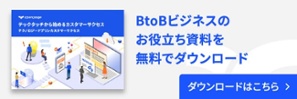「新規事業の営業をしているが、なかなか成果が出ない」「顧客との商談は進むものの、最終的に契約に至らない」こうした悩みを抱えている営業担当者は多いのではないでしょうか。
私がNTT東日本で新規事業開発に携わった14年間で、数多くの新規事業営業の失敗を目の当たりにしてきました。その中で見えてきたのは、新規事業営業で失敗する企業には共通した2つの致命的なパターンがあるということです。
それが「顧客洞察の致命的な不足」と「営業プロセスの主導権完全喪失」です。この2つのパターンを理解し、対策を講じることで、新規事業営業の成功率を大幅に向上させることができます。
新規事業営業が失敗する根本的な理由とは?
新規事業営業の失敗を語る前に、まずその厳しい現実を正しく理解しておく必要があります。
新規事業営業の失敗率93%という現実
新規事業営業は、従来営業と比較して圧倒的に失敗率が高いのが現実です。アビームコンサルティングが2018年に実施した調査(年商200億円以上の780社を対象)によると、新規事業のうち累損解消に至った割合はわずか7%で、93%が失敗に終わっています。
参考:アビームコンサルティング「新規事業取り組み実態調査」https://www.abeam.com/jp/ja/insights/new_business_research/
従来営業との成功率比較
- 従来営業の成約率:30-50%(業界・商材により変動)
- 新規事業の成功率:7%(アビームコンサルティング調査)
- 新規事業で単年度黒字達成:さらに低い割合(同調査)
この圧倒的な差が生まれる理由は、単純に商品力や営業スキルの問題ではありません。新規事業営業には従来営業とは全く異なる構造的課題が存在するからです。
失敗する企業の共通点
- 従来の営業手法をそのまま適用している
- 商品説明中心のプレゼンテーションに依存している
- 顧客の表面的なニーズにとらわれている
- 長期的な関係構築よりも短期的な成果を重視している
よくある失敗パターンの表面的対策では解決しない理由
新規事業営業の失敗例として、よく「市場調査不足」「資金不足」「人材不足」などが挙げられます。確かにこれらも重要な要素ですが、これらの表面的な課題を解決しただけでは、新規事業営業の成功にはつながりません。
表面的な課題への対策例
- 市場調査を徹底的に実施 → それでも顧客ニーズを掴めない
- 営業予算を増額 → 活動量は増えるが成約率は向上しない
- 優秀な人材を投入 → 従来営業の成功者でも結果が出ない
私の経験でも、これらの表面的対策だけでは根本的な解決に至らないケースを数多く見てきました。本質的な問題は、営業アプローチそのものの構造的欠陥にあります。
構造的欠陥の例
- 価値が不明確な商品を従来の説明手法で売ろうとする
- 顧客の潜在ニーズを顕在化させるプロセスが欠如している
- 新規事業特有の不確実性に対応できない営業設計
致命的失敗パターン①:顧客洞察の致命的な不足
新規事業営業で最も多く見られる失敗パターンが、顧客洞察の不足です。これは単純な情報収集不足ではなく、もっと根深い問題です。
表面的な課題しか掴めない洞察不足の正体
新規事業営業で失敗する営業担当者の多くは、顧客の「言葉通り」の課題を鵜呑みにしてしまいます。例えば、顧客が「コスト削減をしたい」と言った場合、その言葉そのままを課題として受け取り、コスト削減効果を前面に出した提案を行います。
しかし、新規事業営業では、顧客自身も自分の真の課題を正確に把握していないケースがほとんどです。
洞察不足の具体例
- 顧客の発言「業務効率化を進めたい」
- 表面的理解コスト削減とスピード向上の提案
- 真の課題意思決定プロセスの複雑化による組織力低下
私がNTT東日本で経験したある自治体案件では、当初「申請処理の効率化」というニーズを伺っていました。しかし、深く掘り下げていくと、真の課題は「住民満足度向上による地域活性化」であり、効率化はその手段の一つに過ぎませんでした。
3階層理解の欠如による問題
- 立場理解の不足組織内での役割や制約を理解していない
- 動機理解の不足なぜその課題に取り組む必要があるかを把握していない
- 認知理解の不足相手がその課題をどう分析・解釈しているかを理解していない
洞察不足が引き起こす3つの破綻シナリオ
顧客洞察が不足した営業活動は、以下の3つのシナリオで必ず破綻します。
シナリオ1:価値提案のミスマッチ
- 顧客の表面的ニーズに基づいた提案を行う
- 実際の決裁者や影響力者の真のニーズとズレている
- 提案内容は理解されるが、購買意欲につながらない
シナリオ2:競合他社との差別化失敗
- 顧客の課題認識が浅いため、競合との違いを説明できない
- 価格競争に巻き込まれる
- 「他社でも同じことができる」と判断される
シナリオ3:顧客の意思決定プロセス誤読
- 誰が真の決裁者かを把握できていない
- 決裁に必要な社内調整プロセスを理解していない
- タイミングや進め方を間違えて商談が停滞
洞察を深める具体的な改善方法
顧客洞察を深めるためには、体系的なアプローチが必要です。私が実践してきた「空雨傘」フレームワークを活用した手法をご紹介します。
空雨傘フレームワークの実践
- 空(事実認識)顧客の現状を多角的に把握
- 雨(解釈・判断)背景にある真の課題を分析
- 傘(対策・行動)解決策と価値提案を構築
仮説検証サイクルの構築
- 事前情報収集による仮説構築
- 初回面談での仮説検証
- 追加調査による仮説修正
- 2回目面談での深掘り
- 洞察の整理と価値提案の精緻化
重要なのは、得られた洞察を必ず文字化し、可視化することです。頭の中だけで理解したつもりになっていても、実際には曖昧な理解に留まっていることが多いからです。
致命的失敗パターン②:営業プロセスの主導権完全喪失
新規事業営業のもう一つの致命的失敗パターンが、営業プロセスの主導権を完全に失ってしまうことです。
サブワーク化による営業プロセス崩壊の実態
新規事業は顧客にとっても未知の領域のため、本業とは別の「サブワーク」として扱われがちです。そうなると、以下のような悪循環に陥ります。
サブワーク化の兆候
- 前回の打ち合わせから2週間以上間が空く
- 顧客からの返答や資料提出が遅れる
- 「忙しくて検討できていない」という返答が増える
- 決裁者との面談がなかなかセッティングされない
私の経験では、新規事業案件で2週間を超える間隔が空いてしまうと、顧客の熱量と優先度が急激に低下し、プロジェクトが自然消滅する確率が大幅に高まります。これは人間の記憶特性に基づく現象で、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが発見した「忘却曲線」によると、2週間後には約80%の情報が忘れられてしまうためです。
参考:Hermann Ebbinghaus「記憶について」(1885) / 詳細は各種心理学文献を参照
プロセス崩壊の段階
- 関心低下期(2-3週間)前回の内容を思い出すのに時間がかかる
- 優先順位低下期(1-2ヶ月)他の業務に埋もれて後回しになる
- 自然消滅期(3ヶ月以上)そもそも検討していたことを忘れる
なぜ新規事業営業では主導権を失いやすいのか?
新規事業営業が従来営業よりも主導権を失いやすい理由は、その構造的違いにあります。
従来営業の場合
- 顧客に明確な課題認識がある
- 解決策の方向性が見えている
- 導入効果が予測しやすい
- 社内での合意形成が比較的容易
新規事業営業の場合
- 顧客の課題認識が曖昧
- 解決策の効果が不透明
- ROIの算出が困難
- 社内での理解を得るのが困難
この違いにより、顧客側の意思決定プロセスが不安定になり、営業側が主導権を失いやすくなります。
主導権喪失の具体的パターン
- 「上司に相談してから返答します」で連絡が途絶える
- 「予算取りができてから再度検討します」で1年以上待つことになる
- 「他の案件が優先なので、少し待ってください」で無期限延期
主導権を取り戻すための実践手法
主導権を維持・回復するためには、戦略的なプロセス管理が必要です。
2週間ルールの科学的根拠と運用 人間の記憶と関心は時間とともに指数的に減衰します。エビングハウスの忘却曲線によると、2週間後には約80%の情報が忘れられてしまいます。
2週間ルール運用方法
- 必ず次回面談を2週間以内に設定
- 面談できない場合は電話やメールで接触
- 毎回、次回までの具体的アクションを明確化
- 相手の負担を最小限に抑えた小さなタスクを設定
「夢を見させる」リターン提示技術 顧客に負荷をかける正当性を示すため、将来の大きなリターンを段階的に提示します。
リターン提示の構造
- 短期リターン(1-3ヶ月)業務改善効果の実感
- 中期リターン(6ヶ月-1年)競争優位性の確立
- 長期リターン(1-3年)業界リーダーとしての地位確立
2つの失敗パターンを同時に解決する統合アプローチ
これまで説明した2つの失敗パターンは、実は密接に関連しています。顧客洞察が不足していると適切なプロセス管理ができず、主導権を失うと深い洞察を得る機会も失われるからです。
洞察力向上と主導権維持を両立させる営業設計
統合的アプローチの原則
- 洞察を深めるプロセス自体を主導権維持のツールとして活用
- 顧客の課題分析を共同作業として位置づけ
- プロセス管理を顧客価値創造の一部として設計
実践手法
- 初回面談で課題の全体像をマッピング
- 2週間後に詳細分析結果を共有
- 4週間後に解決策の方向性を提示
- 6週間後に具体的提案と導入計画を提示
このサイクルにより、洞察を深めながら継続的な接触を維持し、自然に主導権を保持できます。
失敗から成功への転換事例
私がNTT東日本で担当した自治体向けデジタル化支援事業では、当初この2つのパターンで失敗していました。
失敗時の状況
- 表面的な「効率化ニーズ」に基づいた提案
- 1ヶ月以上の間隔での不定期面談
- 顧客任せのプロジェクト進行
改善後のアプローチ
- 3階層での深い顧客理解(住民満足度向上という真の目的を発見)
- 2週間サイクルでの継続的な価値提供
- 段階的リターン提示による動機維持
この改善により、最終的に年間ARR10億円規模の事業立ち上げに成功しました。
まとめ:新規事業営業の失敗を回避するための行動指針
新規事業営業で失敗する2つの致命的パターン「顧客洞察の不足」と「プロセス主導権の喪失」は、相互に関連し合う構造的な問題です。
失敗回避のための行動指針
- 顧客の言葉を鵜呑みにせず、3階層での深い理解を心がける
- 空雨傘フレームワークで洞察を体系的に整理する
- 2週間ルールを厳格に運用し、サブワーク化を防ぐ
- 段階的リターン提示で顧客の動機を継続的に維持する
- 洞察獲得とプロセス管理を統合した営業設計を行う
これらの指針に従って営業活動を見直すことで、新規事業営業の成功率を大幅に向上させることができます。新規事業営業は確かに困難ですが、適切なアプローチを取れば必ず成功に導くことができるのです。
ど、具体的な手法を自社の新規事業営業に取り入れ、競合他社との差別化を実現してください。
この記事を書いた人
|
openpage 事業開発部長 北森雅雄(kitamori masao) NTT東日本で14年間、自治体SE、新規事業開発、デジタルマーケティングを経験し、総額10億円の案件創出や年間ARR10億円規模の事業立ち上げを実現。2025年にopenpageに転職し、現在は事業開発部長として8がけ社会時代の営業DX推進に取り組む。 |
 |
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら