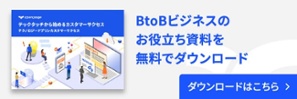新規事業の営業担当になったものの、これまでの営業手法が全く通用せず困惑している営業担当者は多いのではないでしょうか。私がNTT東日本で新規事業開発に携わっていた14年間で最も痛感したのは、従来営業と新規事業営業は根本的に異なるということです。
単純に「新しい商品を売る」だけではありません。新規事業営業では、商品の価値そのものを顧客と一緒に創り上げていく必要があります。本記事では、年間ARR10億円規模の事業立ち上げ経験を基に、新規事業営業の本質的違いと成功のポイントを解説します。
新規事業営業と既存営業の根本的な違いとは?
新規事業営業と従来の既存営業には、営業活動の出発点から大きな違いがあります。この違いを理解せずに従来の営業手法をそのまま適用すると、必ずといっていいほど失敗します。
従来営業は「価値伝達」のスキル勝負
従来営業では、すでに確立された商品やサービスの価値を顧客に正確に伝えることが最重要課題です。営業戦略の核となる要素は以下の通りです。
従来営業の特徴
- 商品の機能や特徴が明確に整理されている
- 豊富な導入事例とROI実績がある
- 競合との比較優位性が数値で示せる
- 標準化された営業プロセスが存在する
例えば、既存のCRMシステムを販売する場合、営業担当者が活用できる材料は豊富です。導入企業の具体的な成功事例、数値で証明されたROI実績、詳細な機能比較表、業界別の最適化提案などです。
営業担当者は、これらの材料を顧客のニーズに合わせて組み合わせ、説得力のある提案を作成します。ここでの成否を分けるのは、情報をいかに魅力的に伝えるかという「伝達スキル」です。
新規事業営業は「価値創造」からスタート
新規事業営業では商品やサービス自体が未完成であったり、そもそも存在していない場合も少なくありません。私がNTT東日本で経験した新規事業でも、最初はプロダクトの核となる価値提案が曖昧で、顧客に説明しても「で、結局何ができるの?」と聞き返されることが頻繁にありました。
新規事業営業の特徴
- 商品・サービスが未完成または存在しない
- 価値提案が言語化されていない
- 成功事例や導入実績がない
- 営業プロセスが標準化されていない
価値創造プロセスの実例 私の経験では、ある自治体向けデジタル化支援サービスの立ち上げで以下のプロセスを経ました。
- 初期状態 「AI活用による業務効率化」という曖昧なコンセプト
- 顧客対話 実際の業務フローと課題を詳細にヒアリング
- 価値発見 効率化以上に「意思決定の質向上」が真のニーズと判明
- 価値言語化 「従来2週間の検討期間が3日に短縮され、政策実行スピードが5倍向上」
新規事業営業では、顧客との対話を通じて価値そのものを発見し、創造していく営業プロセスが必要になります。顧客が気づいていない潜在的な課題を掘り起こし、その課題に対する新しい解決策を一緒に考え、顧客を「共創パートナー」として巻き込む必要があります。
なぜ新規事業営業では従来の営業手法が通用しないのか?
新規事業営業で従来手法が通用しない理由は、商品と顧客の課題認識レベルの両面に根本的な違いがあるためです。
プロダクトの価値が言語化しきれていない現実
新規事業では、商品やサービスの本質的価値がまだ明確に言語化されていないケースが大半です。機能や特徴は説明できても、より深い部分が不明確な状態です。
よくある言語化不足のパターン
- 機能説明 「AIを活用した業務効率化ツールです」
- 特徴説明 「従来より30%効率化できます」
- しかし不明確な部分
- なぜその機能が顧客にとって価値があるのか?
- どのような課題設定においてその価値が最大化されるのか?
- 顧客の業務にどのような変化をもたらすのか?
私の経験では、新規事業の初期段階で最も時間をかけたのが、この価値の言語化作業でした。単に「AIを活用した業務効率化ツール」と説明するのではなく、「従来2時間かかっていた資料作成が15分に短縮され、その時間を戦略的思考に充てることで営業成果が30%向上する」といった具体的な価値を表現できるまで、何度も顧客との対話を重ねました。
顧客の課題認識レベルの違いによる営業アプローチ
従来営業では、顧客がすでに「売上管理を効率化したい」「人件費を20%削減したい」といった明確なニーズを持っています。営業担当者はそのニーズに対する最適解を提示すればよく、比較的分かりやすい営業プロセスになります。
しかし、新規事業営業では、顧客自身も自分の真の課題を正確に把握していない場合が多いのです。表面的には「業務効率化を進めたい」というニーズを表明していても、深堀りすると真の課題は「意思決定の遅さ」「情報共有の不備」「承認プロセスの複雑さ」にあったりします。
私がよく活用していたのは「空雨傘」のフレームワークです。空(事実認識)で顧客の現状を徹底的に把握し、雨(解釈・判断)でその背景にある真の課題を分析し、傘(対策・行動)で新しい価値提案を構築する。このプロセスを顧客と一緒に進めることで、顧客開拓の成功率を大幅に向上させることができました。
新規事業営業で成功するための3つの営業戦略
新規事業営業を成功させるためには、従来営業とは異なる専用の営業戦略が必要です。私の経験から、特に重要な3つの戦略をご紹介します。
相手理解の解像度を劇的に上げる洞察プロセス
新規事業営業では、顧客理解の深さが成否を分けます。表面的な業界知識や基本的な企業情報だけでは不十分です。相手の立場、動機、認知の3階層で理解を深める営業プロセスが必要になります。
立場の理解
単に「IT部門の課長」ではなく、「経営層からデジタル変革を求められているが、現場の抵抗も強く、限られた予算で成果を出さなければならない立場」まで理解を深めます。
動機の理解
なぜその課題に取り組む必要があるのか、背景にある事情を掘り下げます。業績目標だけでなく、個人的なキャリア目標や組織内での立ち位置なども含めて考慮します。
認知の理解
相手がその課題をどのように捉え、原因をどう分析し、解決策をどう考えているかを把握します。ここで重要なのは、相手の課題設定を理解した上で、より深い本質的な課題を提示することです。
このプロセスでは、1回の面談で全てを理解するのは不可能なので、複数回の接触を通じて段階的に理解を深めていきます。そして、得られた洞察は必ず文字化し、可視化して共通認識を構築します。
顧客との価値共創を実現する営業プロセス設計
新規事業営業では、顧客を単なる「売り先」ではなく、価値創造の「パートナー」として位置づける必要があります。顧客が表明する課題をそのまま受け取るのではなく、「なぜその課題が発生するのか」「適切な原因やボトルネックは何か」を一緒に分析します。
私が特に重視していたのは「その場で作り上げる」柔軟性です。事前に準備した資料や提案に固執するのではなく、顧客との対話の中で新しいアイデアや価値提案をリアルタイムで構築していきます。この柔軟性があることで、顧客も積極的に意見を出してくれるようになり、真の共創が実現します。
ただし、この柔軟性は場当たり的な対応とは異なります。空雨傘のフレームワークのように、基本的な思考の型を持ちながら、その中で創造的な対話を展開していくことが重要です。
主導権を維持する営業スケジュール管理術
新規事業営業で最も陥りやすい失敗パターンが、営業プロセスの主導権を顧客に渡してしまうことです。新規事業は顧客にとっても未知の領域のため、本業とは別の「サブワーク」として位置づけられがちです。
この課題を解決するために、私が実践していたのが「2週間ルール」です。前回の打ち合わせから2週間を超えると、顧客の熱量と優先度が急激に低下します。人間の記憶は時間の経過とともに指数的に減衰し、新しい業務や課題が次々と発生して優先順位が変動するためです。
サブワーク化を防ぐ具体的手法
- 2週間以内に達成可能な小さな目標を設定
- 各マイルストーンでの成果物を明確化
- 次回までの具体的なアクションプランを合意
- 新規事業の検討プロセス自体が、顧客の本来業務にもプラス効果をもたらすよう設計
顧客に負荷をかける正当性を示すため、「大きなリターンへの夢」を具体的に提示することも重要です。「このプロジェクトにより、3ヶ月後は処理時間50%短縮で年間200万円のコスト削減、1年後は新サービスにより年間売上1,000万円増加、3年後は地域でのデジタル化リーダーとしてのブランド確立」といった段階的リターンを示します。
まとめ:新規事業営業で競合他社と差別化を図る方法
新規事業営業と従来営業の本質的違いを理解し、適切なアプローチを取ることで、競合他社との明確な差別化を実現できます。
新規事業営業成功の3つの鍵は、価値創造マインド(商品を売るのではなく、価値を共創する)、深い顧客洞察(3階層での理解を深める)、主導権の維持(2週間ルールと明確なマイルストーン設定)です。
従来の営業手法を使う競合他社に対して、課題設定の再定義(顧客の真の課題を発見し、言語化する)、価値共創プロセス(顧客をパートナーとして巻き込む)、継続的な関係構築(単発の取引ではなく、長期的な価値創造)で圧倒的な差別化を図ることができます。
新規事業営業は確かに難易度が高い営業活動ですが、その分、成功した際の顧客との関係性は従来営業では得られない深いものになります。今回解説した空雨傘フレームワークや2週間ルールなど、具体的な手法を自社の新規事業営業に取り入れ、競合他社との差別化を実現してください。
この記事を書いた人
|
openpage 事業開発部長 北森雅雄(kitamori masao) NTT東日本で14年間、自治体SE、新規事業開発、デジタルマーケティングを経験し、総額10億円の案件創出や年間ARR10億円規模の事業立ち上げを実現。2025年にopenpageに転職し、現在は事業開発部長として8がけ社会時代の営業DX推進に取り組む。 |
 |
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら