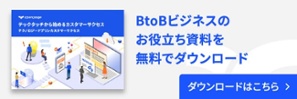株式会社openpage代表取締役の藤島誓也です。私は地方出身で、都心に憧れて札幌、東京へと移り住んできました。そんな自分が今、ベンチャー企業の経営者として行政の地方創生に関わるようになりました。人生とは不思議なものです。
弊社openpageは「デジタルセールスルーム」を開発しています。企業がお客様専用のポータルサイトで提案内容やコンテンツを共有し、関係性を構築するツールです。行政との仕事が始まったのは、NTT東日本で行政案件を手がけていた北森さんが転職してきて「行政もあらゆるステークホルダーと関係構築をしている。openpageのノウハウが活かせるのでは」と提案してくれたのがきっかけでした。
地元は成功しているけれど
地方創生に関わる中で、私がまず思い浮かぶのは故郷の北海道紋別市です。ふるさと納税で全国2位という実績を持つ街で、港町で漁業が盛んという強みがあります。確かに成功事例と言えるでしょう。
ただ、これは地の利があったからこその成功です。すべての街に紋別のような特産品があるわけではありません。もっと再現性のある、どの街でも応用できる成功要素はないのだろうか。そんな疑問を抱いていました。
実は身近な場所にヒントがあった
そんな時、改めて注目したのが私がもともと週末を過ごしている西荻窪という街でした。関係構築の専門家として観察してみると、ここには興味深い現象が起きていたのです。
先週末、いつものように西荻窪を歩いていて、まだ入ったことのない5labというお店を見つけました。ふらりと入ると「お兄さん初めてですか?」と気さくに声をかけてくれます。
メニューの「ゴラボザーグカレー」が気になって尋ねると、「剛さんのラボ的なカレー」という意味。剛さんが店主の名前で、実験的に作り上げたカレーでした。
ここで私は営業のプロとして、はっとしました。
帰宅後に調べると、剛さんの人柄やお店の哲学を、お客様が個人的にブログで発信している。店主の価値観が自然とコンテンツ化され、街の魅力として拡散されているんです。これは営業で理想とする「顧客による自発的な推奨」そのものでした。
営業では「情報の非対称性」を解消することが信頼構築の第一歩とされます。西荻窪の店では豊富な情報が得られるからこそ「ここまで深く知れるなら、自分も開示しよう」という気持ちが生まれるのです。
西荻窪という「関係構築の教科書」
5labでの体験をきっかけに、西荻窪を意識的に観察するようになりました。すると、この街全体が関係構築の教科書のような場所だと気づいたのです。
個人飲食店のネットワークが豊かで、どの店でも絶妙な距離感で声をかけてくれます。常連も初回客も分け隔てなく迎え入れてくれる。安堵感があり、受け入れられている感覚、一員になった気分になれるのです。
カスタマーサクセスでいう「オンボーディング」が数分で完了している。これは店主が意識的に「心理的安全性」を創出しているからでしょう。
店主が先に自分のストーリーや価値観を語る。営業理論でいう「ギブ・ファースト」の原則を無意識に実践しているのです。これが相手の警戒心を解き、対等な関係性を築いています。
東京では知らない人と話すことが憚られがちですが、西荻窪には「優しい世界観」があります。個人経営の個性的な店が密集する独特の文化が、この空間を作り出しているのです。
学術的にも注目される街
この文化は自然発生的に生まれました。旧建物の残存率が高く、偶発的にこのような文化が育まれたのです。
上智大学のジェームス・ファーラー教授は、この街を「西荻町学(Nishiogiology)」と称して研究しています。実際に西荻窪に通い、飲食店主や利用者へのインタビューと参与観察を実施。「顔が見えるつながり」「店主同士の情報ネットワーク」「住民間の協力関係」を詳細に記録しています。
西荻窪では昔から「住民の暮らしや街の個性を守る」ことを重視した活動が続いており、「行政主導ではなく、住民の声で未来像を描く」プロセスが重視されてきました。
人口減少社会の希望
地方出身の私にとって、西荻窪は人口減少社会の課題解決への重要なヒントを与えてくれます。小さな飲食店や地域文化のネットワークが、住民同士の交流や支え合いを生みやすくし、コミュニティの「社会資本」を維持しているからです。
多様で自発的なカルチャーや温かな人間関係は、「この街で暮らしたい」「住み続けたい」と思わせる力があります。人口減少下でもコミュニティの結束と誇りを保っています。
営業の観点から見ると、西荻窪は「顧客ロイヤルティ」の最高峰を実現している街だと言えます。顧客満足を超えた「顧客感動」、さらには「顧客の自発的な推奨行動」まで生み出している。しかも、それが商業的な戦略ではなく、自然発生的に起きているところに驚かされます。
日本各地で「数を増やす」よりも「既存住民の暮らしやすさ」を大切にする方針が注目されていますが、西荻窪はそのモデルケースになり得るでしょう。
営業から学ぶ街づくりの鉄則
営業では「初回訪問で契約を取ろうとするな」が鉄則です。まずは信頼関係を築く。これは街づくりでも同じはずです。
ところが多くの自治体が「移住してください」「観光に来てください」といきなり売り込んでいます。立派なパンフレットを作り、補助金制度を並べ、移住フェアでプレゼンをする。しかし、まずは「この街の人たちを知ってもらう」段階が必要なのではないでしょうか。
西荻窪が素晴らしいのは、誰も「住んでください」と言わないことです。店主たちは自分の価値観や想いを自然に語り、来た人がそれに共感して「この街っていいな」と思う。そして自発的に「また来たい」「住んでみたい」と感じるのです。
関係構築の専門家として見ると、これこそが理想的な「ナーチャリング(育成)」のプロセスなのです。
これからの街づくりへ
この西荻窪の奇跡を他の街でも実現できるのでしょうか。私たちopenpageでは、デジタルセールスルームで培ったノウハウを街づくりに応用しようと考えています。
重要なのは「個別の提案とコンテンツ化」です。単にパンフレットやガイドを用意するだけでは響きません。西荻窪の店主たちが無意識に行っている「踏み込んだ提案」と「価値観の共有」を、テクノロジーで支援するのです。
重要なのは「スケーラブルな親密さ」の実現です。テンプレート的な提案を繰り返すのではなく、その街、その人に合わせた個別のコンテンツを生み出す。西荻窪のような顔の見える関係性を、デジタル上でも再現できるはずです。
これは単なるデジタル化ではありません。関係構築の本質である「相互理解」と「信頼醸成」を、テクノロジーで増幅させる挑戦です。西荻窪の店主たちが「この人にはこの話をしよう」と直感的に判断しているように、データとコンテンツを活用して、その街ならではの魅力を一人ひとりに合わせて伝えていく。そんな仕組みを作りたいのです。
都市部に憧れて故郷を離れた私だからこそ、今度はその経験を活かして、地方の魅力を再発見し、つながりを生み出すお手伝いができればと考えています。
あなたの街にも、きっと価値観や想いを持った個人事業主や店主がいるはずです。まずはその人たちの声に耳を傾け、ストーリーを聞くことから始めてみませんか。そこに、その街ならではの魅力と、人を惹きつける力が眠っているはずです。
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら