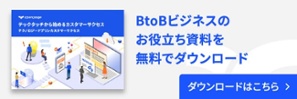「来月の基幹システム更改の件、技術的な詳細はプロジェクトマネージャー(以下、PM)の田中さんから説明してもらえますか?私では分からない部分もあるので...」
大型SI案件の重要な局面で、このような発言をしたことはありませんか?月末の受注目標がかかった既存システムの更改商談で、SIer営業担当者が技術的な会話を避け、PMやプリセールスに主導権を委ねてしまう状況です。
この問題は、単なる営業スキルの不足ではありません。SI業界に根深く存在する構造的課題が、SIer営業を「御用聞き」の立場に追い込んでいるのです。本記事では、SI業界での14年間の現場経験を基に、SIer営業がPM・プリセールス依存に陥る真の要因と、営業本来の価値を取り戻すための実践的な脱却法をご紹介します。
SIer営業が「御用聞き化」してしまう3つの現実
既存案件でPMが実質的な顧客窓口になる構造
SIer営業の売上の大部分を占めるのは、過去に構築したシステムの保守・更改や追加開発です。しかし、これらの既存案件では、技術的な知識を持つPMが日常的に顧客との調整を行っているため、自然とPMが実質的な顧客窓口となってしまいます。
この構造の問題点:
- SIer営業は月1回の定例会議への参加程度に留まる
- 顧客の本音や経営課題を聞く機会を失う
- 契約更新や価格交渉のタイミングを逸する
- 技術的な会話になると「PMから後日連絡します」が口癖に
実際の現場では「お客さんはPMの○○さんとよく話しているから、SIer営業の私が口を出すのは...」という状況が日常化しています。これにより、SIer営業本来の価値である戦略的な関係構築や経営課題の発見機会を失っているのです。
プリセールス機能の理想と現実のギャップ
2016年頃から多くのSI企業がプリセールス機能を設置し始めましたが、理想的な機能分離と現場の実情には大きな乖離があります。
理想の役割分担:
- SIer営業:顧客関係構築、経営課題発見、契約交渉
- PM:プロジェクト管理、技術的品質保証
- プリセールス:技術提案支援、RFP対応
現場の実態:
- プリセールス機能はあるが「兼務」で終わっている
- 結局PMがSIer営業支援もプリセールスも担当
- 「できる人」に全てが集中する状況が継続
この結果、SIer営業はますます技術的な会話を避けるようになり、顧客との深い関係構築ができなくなっています。機能は分離されたものの、人的なリソース配置は従来のままという企業が圧倒的に多いのが現実です。
複雑な既存ベンダとの関係に圧倒されるSIer営業
SI案件特有の複雑性が、SIer営業の思考停止を招いています。複数ベンダにまたがる契約関係、バラバラの保守期間・更新タイミング、段階的移行における責任範囲の曖昧さなど、通常の営業案件とは比較にならない複雑性に直面します。
複雑化の具体例:
- 開発・保守・運用が異なるベンダで契約期間もバラバラ
- システム間連携により他社技術への依存関係が発生
- 長期契約により既存ベンダの既得権益が強固
- 段階的移行の責任範囲が不明確
本来であれば、この複雑性を整理・単純化し、自社に有利な形で再構築することがSIer営業の腕の見せ所です。しかし、多くのSIer営業がこの複雑性に圧倒され、「技術的に難しいからPMに判断を委ねる」という思考停止状態に陥ってしまいます。
なぜSIer営業はPM・プリセールス依存体質に陥るのか
技術解像度の低さが生む悪循環
SIer営業の根本的な問題は、営業担当者の技術解像度の低さにあります。システムの基本的な仕組みや契約構造を理解していないため、顧客との技術的な会話を避け、PMやプリセールスに頼らざるを得ない状況が生まれます。
悪循環の構造:
- 技術理解不足 → 技術的会話を避ける
- PMに依存 → さらに技術に触れる機会が減る
- 顧客との接点減少 → 経営課題を把握できない
- 提案力低下 → さらにPMに依存する
この悪循環により、SIer営業は徐々に「御用聞き」の役割に限定されていきます。
「できる人」への集中が生む組織的な問題
多くのSI企業では、技術と営業の両方をこなせる「スーパーPM」や「技術営業」に案件が集中する現象が起きています。
「できる人に集中」の弊害:
- 該当者の負荷が限界を超える
- 他のメンバーのスキル向上機会が失われる
- 組織全体のレベルアップが阻害される
- 属人化により業務継続性にリスクが発生
短期的には効率的に見えるこの構造が、長期的には組織全体の営業力低下を招いています。また、集中される側の負担も限界を超え、優秀な人材の流出リスクを高めています。
既存ベンダ切り替えの困難さを理解していないSIer営業
SI業界最大の特徴は、既存ベンダとの切り替えが極めて困難であることです。しかし、多くのSIer営業がこの困難さを正しく理解せず、適切な攻略戦略を立てられていません。
既存ベンダ切り替えが困難な理由:
- システムの技術的依存関係
- 移行コストとリスクへの懸念
- 長期契約による既得権益
- 顧客側の意思決定プロセスの複雑さ
本来であれば、この構造的な困難さを理解した上で、段階的な攻略戦略を立てることがSIer営業の重要な価値です。しかし、「なぁなぁになりがち」と諦めてしまうSIer営業が多いのが実情です。
SIer営業の真の価値とは何か
複雑性のシンプル化による顧客価値創出
SIer営業の最も重要な価値は、複雑に絡み合ったシステム構造や契約関係を、顧客にとって理解しやすい形にシンプルに再定義することです。これは、技術者には難しい「ビジネス視点での整理能力」が求められる領域です。
シンプル化の具体例:
- 複数ベンダの契約を統一的な視点で整理
- 技術的依存関係をビジネスリスクとして翻訳
- 段階的移行の優先順位を経営効果で説明
- 投資対効果を分かりやすい指標で提示
既存ベンダ領域への戦略的攻略
SIer営業の腕の見せ所は、他社が長年構築してきた既得権益に対する戦略的なアプローチです。これは単なる価格競争ではなく、顧客の経営課題解決という価値提案で勝負する高度な営業技術です。
攻略戦略の要素:
- 既存システムの課題分析と可視化
- 段階的移行によるリスク軽減提案
- 経営効果を重視した投資計画の設計
- 顧客内の意思決定プロセスへの適切な働きかけ
顧客の経営課題と技術課題をつなぐ価値創出
PMやプリセールスが技術的観点から現状を把握する一方で、SIer営業は経営課題の視点から技術課題を翻訳する役割を担います。
価値創出の具体例:
- 技術的制約を事業機会として再定義
- システム投資を経営戦略の一環として位置付け
- 技術的改善を業務効率化効果で定量化
- IT予算を戦略投資として正当化
PM・プリセールス依存から脱却する実践的手法
Step1:営業プロセス節目の会議体設計(今週から実装)
営業、PM、プリセールスが連携する会議体を業務の節目に設計します。重要なのは、営業が技術的な「知識」を増やすことではなく、顧客の経営課題を技術的解決策につなげる「翻訳力」を身につけることです。
設計すべき4つの定期会議体:
① コンセプトレビュー(提案前・月2回)
- 営業の本来の役割: 「なぜこの技術提案が顧客の経営目標達成につながるのか?」のストーリー構築
- PMの役割: 技術的実現性とリスクの評価
- 会議の成果: 技術仕様ではなく「経営価値実現のシナリオ」の合意
② 提案審議(提案書完成前・案件毎)
- 営業が説明すべきこと: 技術的詳細ではなく「この技術選択により、顧客にどんなビジネス価値を提供できるか」
- 審議の焦点: 競合他社ではなく、顧客の経営課題解決における自社提案の独自価値
- 営業の成長指標: 技術用語の理解度ではなく、技術価値を経営言語で説明できる力
③ 提案後振り返り(結果判明後・案件毎)
- 重点分析項目: 「技術的優位性は伝わったか?」ではなく「経営価値が響いたか?」
- 営業の学習: 技術説明の巧拙ではなく、経営課題との接続の成否を検証
④ プロジェクト審議会(受注後・プロジェクト毎)
- 営業の継続価値: プロジェクト進行を顧客の経営成果に翻訳し、継続的な関係強化を図る
各会議の運用哲学: 技術的な正確性よりも「顧客の経営者が理解し、納得できる形での価値提示」を重視します。PMやプリセールスが技術的詳細を担保し、営業は徹底的に「顧客価値の翻訳者」に特化します。
Step2:「翻訳力」向上のための段階的な思考転換(3ヶ月サイクル)
技術知識の暗記ではなく、経営課題と技術解決策を結びつける思考パターンを身につけます。
1ヶ月目標:
- 「このシステムはOracleを使っています」→「このシステム選択により、5年間の運用コストを30%削減できます」への表現転換
- 技術的制約を「できない理由」ではなく「段階的実現のロードマップ」として再構成
- 顧客の予算制約を技術仕様調整によるコストコントロール提案に転換
2ヶ月目標:
- 競合技術との比較を「機能差」ではなく「顧客の事業戦略との適合度」で整理
- 既存システムの制約を「移行リスク」ではなく「段階的価値実現の機会」として再定義
- 技術的な複雑性を顧客の組織体制に合わせた「実現可能な改善計画」に翻訳
3ヶ月目標:
- システム投資を単なるコストではなく「経営戦略実現の基盤投資」として位置づけ
- 技術的優位性を「競合との差」ではなく「顧客固有の経営課題解決力」として訴求
- 複雑な既存ベンダ関係を整理し「シンプルで効率的な新体制」への移行価値を提示
実際の思考転換例: 私が担当した20以上の小中学校システム更改案件では、PMからの技術説明「新システムは統一的な管理基盤で運用効率が向上する」を、営業として「各校で異なる保守期間や契約期間を統一し、予算管理の負担を大幅に削減できます。また、実際の使用状況に基づく端末台数の最適化により、無駄な投資を20%削減できます」と翻訳しました。技術的詳細は理解していませんが、教育委員会の最大の悩みである「複雑な契約管理の負担軽減」との接続を重視した結果、総額7億円規模の大型案件で複数校の一括受注を実現できました。
Step3:PM・プリセールスとの協業体制最適化(会議体運用と並行)
会議体の運用を通じて、対立ではなく協業による相乗効果を生み出します。
協業最適化のポイント:
- 営業: 顧客関係構築と経営課題発見、契約条件交渉に集中
- PM: 技術的品質保証とプロジェクト管理、リスク評価に専念
- プリセールス: 技術提案と実現可能性検証、競合技術分析を担当
相互理解促進の仕組み:
- 月次で各職種の成果と課題を共有する場を設定
- 成功案件では必ず「三者協業の成功要因」を整理
- 失敗時も責任追及ではなく「次回の改善点」として議論
段階的な関係改善アプローチ: 既存の「できる人」に対しては感謝を示しながら、段階的に役割分担を最適化していきます。急激な変化は避け、会議体での成功体験を積み重ねることで、自然な形で協業関係を発展させます。
Step4:既存ベンダ攻略の戦略立案
既存ベンダとの競合に勝つための体系的なアプローチを確立します。
実際の成功事例: 私が担当した20以上の小中学校システム更改案件では、既存ベンダが長年の教育現場での運用実績を武器にしていました。しかし、私たちは技術比較ではなく「複雑化した契約・運用体制のシンプル化」という観点で提案を再構成。各校で異なる保守期間のばらつき、過剰な端末台数、複雑な技術要件などの課題を可視化し、統一的な契約体系と実使用に基づく仕様最適化により「7年間の長期運用で総運用費用を30%削減」する提案で受注に成功しました。総額7億円の案件でしたが、技術的優位性ではなく「複雑性の整理による長期的な管理負担軽減」という経営課題解決の視点が決め手となりました。
攻略戦略の具体的な立て方:
- 現状分析(3ヶ月):20以上の小中学校における保守期間、契約期間、端末台数の詳細実態調査
- 複雑性の可視化(2ヶ月):契約・運用の複雑性が教育委員会に与える負担の定量化と改善効果の試算
- 統合提案の策定(1ヶ月):統一契約と仕様最適化による負担軽減提案の完成
- 段階的移行計画(継続):教育現場の継続性を確保した移行スケジュールの設計と実行支援
この6ヶ月間の提案プロセスを通じて、営業として最も重要だったのは「20校以上の複雑に絡み合った契約・技術・運用状況を、教育委員会にとって理解しやすい統一的な視点で整理すること」でした。PMは各校の技術的詳細を正確に把握しましたが、それを「7年間の長期視点での予算最適化」「管理負担軽減」「教育継続性の確保」という教育行政の言葉に翻訳することで、7億円という大型受注を実現できました。
失敗パターンと対策
失敗パターン1:会議体で「技術の勉強会」になってしまう
よくある状況: 会議の焦点が「営業の技術理解度向上」に偏ってしまい、本来の目的である「顧客価値創出」から離れてしまうパターン。営業が技術用語を覚えることに注力し、肝心の「経営価値翻訳」ができなくなる。
対策: 会議で技術的な話が出た際は、必ず「これが顧客の経営にどんなインパクトを与えるか?」「顧客の決裁者にはどう説明するか?」を営業が回答する。技術知識の習得ではなく、価値翻訳力の向上に焦点を当てる。PMやプリセールスには「営業が経営言語で説明できるまで、技術情報を噛み砕いてほしい」と依頼する。
失敗パターン2:PMやプリセールスとの関係悪化
よくある状況: 営業が主導権を取ろうとして技術者との関係が悪化し、協業体制が崩れるパターン。特に「できる人」の機嫌を損ねると組織全体に大きな影響が出る。
対策: 技術者の専門性を尊重しつつ、営業は経営価値創出に集中するという「住み分け」を明確にする。対立ではなく、それぞれの強みを活かす協業体制を構築する。「できる人への感謝」を示しながら、段階的に役割分担を最適化していく。
失敗パターン3:既存ベンダ攻略で無謀な戦いを挑む
よくある状況: 既存ベンダの既得権益の強さを理解せず、価格競争や技術比較で正面から勝負してしまうパターン。
対策: 既存ベンダの強みを正しく分析し、正面からの競合を避けて「経営課題解決」という別次元での価値提案を行う。顧客にとって本質的に重要な課題に焦点を当て、長期的な関係構築を重視する。
まとめ:SI営業の価値を取り戻すために
SI営業が「御用聞き」に陥る問題は、個人のスキル不足だけでなく、業界特有の構造的な課題に起因しています。PM・プリセールス依存から脱却し、営業本来の価値を取り戻すためには:
重要なポイント:
- 技術知識の戦略的習得(完璧を目指さず、翻訳能力を重視)
- 複雑性のシンプル化スキルの向上
- PMやプリセールスとの適切な役割分担
- 既存ベンダ攻略の体系的アプローチ
これらの取り組みを通じて、SI営業は単なる「御用聞き」から、顧客の経営課題解決に貢献する戦略的パートナーへと進化できます。
小さな改善の積み重ねが、やがて大きな競争優位を生み出すでしょう。特にSI営業では、営業・PM・プリセールスの役割分担の最適化が受注の成否を直接左右するため、早期の取り組み開始をお勧めします。
なお、より本格的な営業力強化を検討される場合は、SI営業特化型の支援ソリューションの活用も有効です。PM・プリセールス依存からの脱却と営業主導の案件攻略を実現する、実践的なアプローチにより、上記の効果をさらに加速させることが可能です。
この記事を書いた人
|
openpage 事業開発部長 北森雅雄(kitamori masao) NTT東日本で14年間、自治体SE、新規事業開発、デジタルマーケティングを経験し、総額10億円の案件創出や年間ARR10億円規模の事業立ち上げを実現。2025年にopenpageに転職し、現在は事業開発部長として8がけ社会時代の営業DX推進に取り組む。 |
 |
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら