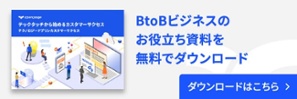ビジネスのデジタル化が加速する現代において、営業活動のあり方も大きく変化しています。従来の対面型営業からオンラインを活用した非対面型営業へのシフトが進む中、企業は効率的かつ効果的な営業手法を模索しています。このような背景から、従来のSFA(Sales Force Automation)だけでは対応しきれない課題が浮き彫りとなり、新たな営業DXソリューションとしてデジタルセールスルーム(DSR)が注目を集めています。
特に日本企業において、2020年に国内初のDSRとしてローンチされた「openpage」は、多くの企業に導入され、従来のSFAを補完あるいは代替するツールとして選ばれるようになってきました。では、なぜopenpageをはじめとするDSRが、SFAより優先して選ばれるようになっているのでしょうか。
2. SFAとDSRの根本的な違い
まず、SFAとDSRの根本的な違いを理解することが重要です。
SFAの特徴と目的
SFAは「Sales Force Automation(営業支援システム)」の略称で、営業活動の管理や効率化を目的としたシステムです。主に以下のような特徴があります。
- 営業プロセスの標準化と管理
- 案件や顧客情報の一元管理
- 売上予測や進捗状況の可視化
- 社内向けの営業活動管理ツール
SFAの主な目的は、営業部門の業務効率化と管理強化にあります。しかし、SFAはあくまで「社内向け」のツールであり、定量データの管理が中心となっています。
DSRの特徴と目的
一方、DSR(デジタルセールスルーム)は「Digital Sales Room」の略称で、営業担当者と顧客が共に利用するプラットフォームです。主な特徴は以下の通りです。
- 顧客ごとにカスタマイズされた専用サイトの構築
- 提案資料や契約書類などの関連情報の一元管理
- 顧客の行動分析(視聴データ)に基づいた提案改善
- 商談議事録や課題整理などの定性的情報の蓄積
DSRは「顧客向け」のツールであり、顧客体験の向上と意思決定の促進を目的としています。つまり、SFAが「社内管理」に重点を置いているのに対し、DSRは「顧客との情報共有基盤」を提供するという根本的な違いがあります。
なぜ今、DSRが必要とされているのか
現代の営業組織は多くの構造的な課題に直面しています。特に以下の課題が深刻化しています。
1. 属人化による組織的リスクの増大
多くの営業組織では、トップセールスの知識やノウハウが個人に依存し、組織全体で共有されていません。この属人化は、担当者の退職や異動時に顧客関係が途切れるリスクを高め、安定した業績を維持する障害となっています。SFAでは商談ステータスなど表面的な情報は記録できても、「どのように提案したか」「なぜ顧客が関心を示したか」という質的な情報は記録できません。
2. 顧客接点の不足による機会損失
オンライン環境への移行が進む中、従来の営業手法では顧客との接点が限られています。McKinsey調査によれば、B2B購買者の70%以上がオンラインセルフサービスを好む一方、多くの企業は依然として対面営業に依存しています。この顧客期待値とのギャップが商談機会の損失を招いています。
3. 不透明な顧客状況把握によるミスマッチ
営業担当者は顧客が本当に何に関心を持ち、どの程度購買検討を進めているのかを正確に把握できていません。そのため、適切なタイミングで適切なアプローチができず、「押し売り」や「フォロー不足」といった顧客不満を招いています。SFAでは商談進捗を記録できても、顧客の検討状況をリアルタイムで把握することはできません。
4. 複雑化する意思決定プロセスへの対応不足
B2B取引では、平均4〜5人の関係者が購買意思決定に関わっています。各関係者は異なる関心事を持ち、異なる情報を求めています。従来の営業手法では、これら複数の意思決定者に対して一貫した情報提供ができず、結果として社内検討が滞り、商談が長期化する傾向があります。
5. デジタル営業データの活用不足
多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を掲げる中、営業活動においては依然としてデータ活用が進んでいません。企業の持つ顧客データは断片的で、営業活動の改善に十分活用されていないのが現状です。これにより、「何が効果的な営業アプローチなのか」を科学的に検証することができていません。
これらの深刻な組織課題に対して、従来のSFAでは十分な解決策を提供できなくなっています。SFAは「誰が、いつ、どの顧客に、いくらの商談を」といった定量データの管理には適していますが、「どのように提案し、顧客がどう反応し、なぜ受注に至ったのか」という定性的な情報の管理には向いていません。
こうした背景から、顧客との情報共有基盤として機能し、商談の質的側面をデジタル化できるDSRが注目されるようになったのです。openpageをはじめとするDSRは、単なる営業ツールではなく、営業組織の構造的課題を解決するためのプラットフォームとして位置づけられているのです。
3. openpageがSFAより選ばれる5つの理由
それでは、具体的にopenpageがSFAより優先して選ばれる理由を5つのポイントから分析してみましょう。
理由1: 顧客視点のデザイン(顧客体験の向上)
openpageは、顧客体験を最優先に設計されています。従来のSFAが営業担当者の社内業務効率化を重視していたのに対し、openpageは顧客がストレスなく情報を受け取り、検討を進められるような設計になっています。
「デジタルを織り交ぜた営業体験」を提供することで顧客との接点を増やし、商談内容の振り返りや社内共有をスムーズにします。こうした顧客視点のデザインは、実際に「受注率25%」という成果につながっています。従来10%だった受注率が、顧客体験の向上により大幅に改善されているのです。
理由2: 情報の一元管理と可視化(商談内容の見える化)
openpageでは、商談の議事録、約束したネクストアクション、提案資料など、営業活動に関わる情報を一元管理できます。従来の「口伝とSFA記録」では状況がわからなかったものが、DSRのログにより詳細に把握できるようになります。
従来のSFAでは、こうした情報は営業担当者のメモや記憶に依存することが多く、情報の欠落や齟齬が生じるリスクがありました。openpageでは、情報を顧客と共有しながら蓄積していくため、双方の認識のズレを防ぎ、スムーズな商談進行を実現します。
また、この情報の一元管理は「属人化しない」営業スタイルを実現します。「人に頼らないと見れない」状態から「いつでも見られる(サービス化)」状態への転換が可能になります。
理由3: 顧客行動の深い理解(視聴データによるインサイト)
openpageの強力な特徴の一つが、顧客の行動分析機能です。「DSR視聴回数」のような指標を通じて、提案内容に対する顧客のアクセス状況を詳細に把握することができます。
これにより「誰が提案に反応した?」「何の提案を見ている?」「いつ提案を見た?」というインサイトを得ることができ、次のアプローチを効果的に行うことが可能になります。顧客接触数とその心理状態の相関から、より効果的な営業アプローチが可能になります。例えば、10件以上の接触があれば「契約推進」フェーズにあると判断できます。
理由4: 営業プロセスの標準化と効率化(データ量の飛躍的増加)
openpageでは営業データが10倍以上になります。従来のSFAでは管理されていなかった「提案データ」「ヒアリングデータ」「情報提供データ」などの詳細な顧客とのやり取りが記録され、より細かな営業組織マネジメントが可能になります。
DSRは営業組織のマネジメント・エンジンとして機能し、「型化」「運用改善」「マネジメント」「育成」などの機能を果たします。これにより、トップセールスの知見やベストプラクティスを組織全体に展開し、営業品質の標準化と底上げを図ることが可能になります。
理由5: カスタマーサクセスへの拡張性(営業DXの実現)
openpageは営業のデジタルサービス化を実現します。従来の「一部デジタル営業」から、DSRによる「デジタルの顧客体験」へと転換することで、属人化しない継続的な顧客関係構築が可能になります。
営業スタイルは「アナログ営業(口頭で会話)」から「デジタル営業(PCでデジタル化)」を経て、現在は「DX営業(DSRで営業DX)」という第三世代に進化しています。「デジタル上で4〜5倍の顧客接点増」というデータからもわかるように、従来のSFAよりも顧客との接点を大幅に増やすことができます。これにより、初期販売だけでなく、継続的な取引拡大につなげることができるのです。
4. openpageによる具体的な成果事例
次に、openpageを導入した企業がどのような成果を得ているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
事例1: 受注率の向上
多くの企業がopenpageの導入により、受注率の向上を実現しています。ある企業では、openpageを活用した顧客専用ページの提供により、従来の営業手法と比較して受注率が10%から25%へと大幅に向上しました。
これは、顧客が商談内容を何度も振り返り、社内での検討や稟議を進める際に、必要な情報にスムーズにアクセスできるようになったことが大きな要因です。また、営業担当者も顧客の関心事や検討状況を把握できるため、適切なタイミングでのフォローアップが可能になり、結果として受注率の向上につながっています。
事例2: 営業サイクルの短縮
openpageの導入により、営業サイクル(初回接触から受注までの期間)の短縮にも成功している企業があります。ある製造業では、従来3ヶ月程度かかっていた商談期間が、平均して2ヶ月程度に短縮されました。
これは、顧客との情報共有がスムーズになり、意思決定に必要な情報が迅速に提供できるようになったことが要因です。また、顧客の閲覧データに基づいて、関心度の高い顧客に優先的にアプローチすることで、営業リソースの最適配分が可能になったことも寄与しています。
事例3: 取引規模の拡大
openpageの活用により、顧客との取引規模の拡大に成功している企業も少なくありません。あるサービス業では、既存顧客との取引額が導入前と比較して平均1.2倍に増加したという結果が出ています。
これは、商談内容の可視化と顧客ニーズの深い理解により、追加提案の機会が増えたことが要因です。また、顧客との信頼関係が強化されたことで、新たなプロジェクトや追加サービスの導入が進みやすくなったという側面もあります。
事例4: 属人化の解消
営業活動の属人化は多くの企業が抱える課題ですが、openpageの導入によりこの課題を解決している企業も増えています。ある情報通信企業では、トップセールスのノウハウを組織全体に展開することで、営業担当者間の成績のばらつきが減少したという報告があります。
これは、openpageのテンプレート機能を活用し、成功事例の商談プロセスや提案内容を標準化したことが要因です。また、商談内容の可視化により、マネージャーが適切なタイミングでフィードバックを提供できるようになり、組織全体の営業力底上げにつながっています。
事例5: 顧客満足度の向上
営業ツールの効果として見落とされがちですが、openpageの導入により顧客満足度が向上したという事例も少なくありません。ある企業では、顧客からの評価スコアが導入前と比較して20%向上したという結果が出ています。
これは、顧客が必要な情報にストレスなくアクセスできるようになったことや、商談内容の透明性が確保されたことが要因です。また、顧客の行動データに基づいた適切なフォローアップにより、「押し売り」ではなく「伴走型」の営業スタイルが実現したことも顧客満足度向上に寄与しています。
5. openpageとSFAの連携・共存戦略
openpageをはじめとするDSRの導入を検討する際には、既存のSFAを完全に置き換えるというわけではありません。多くの企業では、openpageとSFAを連携させながら、それぞれの強みを活かした運用を行っています。ここでは、両ツールを効果的に組み合わせる方法について考えてみましょう。
SFAとDSRの役割分担
効果的な連携のためには、まずSFAとDSRの役割分担を明確にすることが重要です。役割分担は以下の通りです:
SFAの役割(定量データ・社内管理):
- 商談ステータスの管理(案件の進捗状況の可視化)
- 契約金額の管理(売上予測と数値管理)
- 営業活動の基本記録
- 社内向けの定量的な管理
DSR(openpage)の役割(定性データ・社外管理):
- 提案内容の詳細な記録と共有
- 情報提供の管理(資料、事例、製品情報など)
- 顧客の反応や行動の計測(カスタマー・レビューデータ:CRD)
- 顧客向けの定性的な情報提供
このように、SFAは「社内の定量管理」、DSRは「顧客との定性的な情報共有」という役割分担を明確にすることで、両ツールの強みを最大限に活かすことができます。
両ツールを効果的に組み合わせる方法
SFAとDSRを効果的に組み合わせるためには、以下のようなアプローチが考えられます。
- データ連携の最適化 SFAとDSRは「連携」することで相乗効果を発揮します。例えば、顧客情報や商談ステータスはSFAで管理し、それをDSRに連携させることで、二重入力を防止し営業担当者の負担を軽減できます。
- プロセスの整合性確保 顧客の検討状況(興味→検討→受注)に合わせた営業プロセス(初回商談→2回目商談→3回目商談)とDSRのコンテンツを整合させることが重要です。例えば、SFAで定義された各商談ステップに応じて、DSRでどのようなコンテンツを提供するかを明確にしておくことが有効です。
- 「営業データ」の統合活用 SFAの定量データとDSRの定性データを「営業データ」として統合的に活用することで、より高度な営業マネジメントが可能になります。例えば、「どの提案内容が受注率向上に寄与しているか」といった分析ができるようになります。
相乗効果を最大化するための運用のポイント
SFAとDSRの相乗効果を最大化するためには、以下のような運用上のポイントが重要です。
- 顧客接触KPIの設定 顧客接触は最低「10回」、できれば「25回」を目指すことが重要です。DSRの視聴回数データを活用して、顧客がどの程度提案内容を確認しているかを測定し、適切なフォローを行うことが効果的です。
- 顧客心理の理解と対応 顧客接触数からある程度顧客の心理状態を推測できます。例えば、0〜2件であれば「興味はあるが検討段階ではない」、10件以上であれば「契約推進フェーズ」と判断できます。この情報をSFAの商談ステージと連携させることで、より正確な営業予測が可能になります。
- プロセスとコンテンツの最適化 顧客の状況(無関心→課題認識→情報収集→比較検討→契約)に合わせて、適切なコンテンツをDSRで提供することが重要です。SFAで管理する商談プロセスとDSRのコンテンツ構成を連携させることで、顧客の状況に最適化された提案が可能になります。
このように、SFAとDSRを適切に役割分担し、効果的に連携させることで、営業活動の質と効率を飛躍的に高めることができるのです。
6. 導入のステップと成功のポイント
openpageをはじめとするDSRの導入を検討する際には、段階的なアプローチと明確な成功指標の設定が重要です。ここでは、DSR導入のステップと成功のポイントについて解説します。
自社の課題を明確にする
DSR導入の第一歩は、自社の営業活動における課題を明確にすることです。例えば、以下のような視点から課題を洗い出すことが有効です。
- 商談の成約率は満足できるレベルか
- 営業サイクルは適切な長さか
- 顧客との信頼関係は十分に構築できているか
- 営業活動の属人化が進んでいないか
- 顧客体験に課題はないか
これらの課題を具体的に把握し、DSR導入によってどの課題を解決したいのかを明確にすることで、導入後の効果測定がしやすくなります。
小規模なPoC(実証実験)からスタート
DSRの導入は、一部の営業チームや特定の顧客セグメントを対象とした小規模なPoCからスタートすることをおすすめします。これにより、少ないリスクで効果を検証し、本格導入に向けた知見を蓄積することができます。
PoCの実施にあたっては、以下のポイントに留意することが重要です。
- 明確な成功指標の設定 受注率の向上、商談期間の短縮、顧客満足度の向上など、具体的な成功指標を設定します。
- 対象範囲の適切な選定 新規開拓営業か既存顧客営業か、特定の商材か全商材かなど、対象範囲を適切に選定します。
- 期間の明確化 3ヶ月〜6ヶ月程度の期間を設定し、その間の効果を測定します。
- 運用ルールの策定 誰がどのようなタイミングでDSRを活用するか、明確な運用ルールを策定します。
成功事例の横展開
PoCで効果が確認できた後は、その成功事例を組織全体に横展開していきます。その際、以下のポイントに留意することが重要です。
- 成功事例の具体化と共有 PoCで得られた成功事例を具体的なストーリーとして共有し、DSRの有効性を実感してもらいます。
- 段階的な展開計画の策定 一度に全組織に展開するのではなく、段階的な展開計画を策定し、着実に浸透させていきます。
- KPIの設定と進捗管理 組織全体への展開にあたっては、明確なKPIを設定し、定期的に進捗を管理します。
- サポート体制の構築 導入初期は特に手厚いサポートが必要です。質問や課題に迅速に対応できる体制を構築しましょう。
組織文化の醸成
DSRの効果を最大化するためには、ツールの導入だけでなく、それを支える組織文化の醸成も重要です。特に以下のような文化を育むことが効果的です。
- 顧客中心の思考 「売ること」だけでなく「顧客の成功を支援すること」を重視する文化を育みます。
- データドリブンな意思決定 感覚や経験だけでなく、データに基づいた意思決定を重視する文化を育みます。
- 知識共有と協働 個人の成果だけでなく、組織全体の知識共有と協働を重視する文化を育みます。
- 継続的な学習と改善 成功事例や失敗事例から学び、継続的に改善していく文化を育みます。
このように、段階的なアプローチと明確な成功指標の設定、そして支援的な組織文化の醸成によって、DSRの導入効果を最大化することができるのです。
7. まとめ:営業DXの未来とopenpageの可能性
最後に、営業DXの未来とopenpageの可能性について考えてみましょう。
営業スタイルの変革
デジタル技術の進化と顧客行動の変化により、営業スタイルは大きく変革しています。従来の「プッシュ型」の営業から、顧客のニーズに寄り添い、価値を共創する「パートナー型」の営業へのシフトが進んでいます。
openpageをはじめとするDSRは、このような営業スタイルの変革を支援するツールとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。特に、顧客との情報共有と透明性の確保、顧客行動の深い理解と適切なアプローチの実現など、「パートナー型」営業に不可欠な要素を支援する機能が評価されています。
データドリブンな営業への進化
営業活動におけるデータ活用の重要性も高まっています。従来の「勘と経験」に頼った営業から、データに基づいた科学的なアプローチへの転換が進んでいます。
openpageは、顧客の行動データを詳細に把握し、そのデータに基づいた最適なアプローチを実現するツールとして、データドリブンな営業の進化を支援しています。今後は、AIやマシンラーニングの技術を活用した予測分析や最適化機能の強化が期待されます。
顧客との共創による価値創出
最終的に、営業DXの目指すべきゴールは、顧客との共創による新たな価値の創出です。単なる製品やサービスの提供を超えて、顧客の課題解決と成功を支援するパートナーとしての役割が求められています。
openpageは、顧客との対話と協働を促進し、共創による価値創出を支援するプラットフォームとしての可能性を秘めています。今後は、単なる営業支援ツールから、顧客との共創プラットフォームへと進化していくことが期待されます。
このように、営業DXの未来において、openpageをはじめとするDSRは中心的な役割を担っていくでしょう。従来のSFAを超え、顧客との新たな関係性を構築し、持続的な成長を実現するための重要なツールとして、その存在感はますます高まっていくことでしょう。
8. 参考データ
業界統計
- デジタルセールスルーム(DSR)市場は2022年に前年比約300%の市場成長を遂げており、2024年には30社以上のプレイヤーが参入するまでに拡大している。
- B2B取引において、購買決定に関わる意思決定者の数は平均4.6人と言われており、複数のステークホルダーへの効果的な情報提供が課題となっている。
- リモートワークの普及により、営業活動の70%以上がオンラインで行われるようになっており、デジタルツールの重要性が高まっている。
導入企業の声
「openpageを導入したことで、顧客との商談内容の共有がスムーズになり、社内での稟議プロセスが格段に効率化されました。結果として、商談期間が約30%短縮され、受注率も向上しています。」
「従来のSFAでは把握できなかった『顧客が何に関心を持っているか』という情報がopenpageによって可視化され、的確なフォローアップが可能になりました。特に大型案件では、複数の意思決定者のそれぞれの関心事に合わせた提案ができるようになり、成約率が大幅に向上しています。」
「営業活動の属人化が課題でしたが、openpageのテンプレート機能を活用することで、トップセールスのノウハウを組織全体に展開することができました。結果として、営業担当者間の成績のばらつきが減少し、組織全体の生産性が向上しています。」
詳細情報の入手方法
openpageの導入を検討されている企業様向けに、以下の資料をご用意しています。
- 製品資料:openpageの機能や特徴を詳細に解説した資料
- 導入成功ガイドブック:様々な企業様にて約束された成功ノウハウがまとまった資料
- 費用対効果歯0と:openpageの導入による具体的なROIを試算した資料
また、無料トライアルも実施しておりますので、実際に使用感を確かめたい方はぜひお申し込みください。専任のサポート担当者が導入をサポートいたします。
デジタル化が進む現代の営業環境において、従来のSFAだけでは対応しきれない課題が増えています。openpageをはじめとするデジタルセールスルームは、顧客体験の向上と営業効率の最大化を両立する新しいソリューションとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。
自社の営業課題を見つめ直し、次世代の営業スタイルを実現するための一歩として、ぜひopenpageの導入をご検討ください。
国内で最も選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら