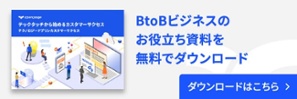SIer営業に携わる方なら、一度は「技術的な詳細はPM(プロジェクトマネージャー)から」「システムの仕様はプリセールスに確認します」といった言葉を使ったことがあるのではないでしょうか。顧客からの技術的な質問に即答できず、持ち帰らざるを得ない場面。これは個人のスキル不足というより、SI業界が30年以上抱え続けている構造的な問題の表れです。
実は、この技術者依存体質には、1990年代のバブル崩壊から始まった日本のIT業界特有の歴史的背景があります。優秀な技術者が受注した案件が、人材の異動後も契約だけが慣性で継続し、営業は技術的な中身を理解できないまま「御用聞き」に甘んじる。この構造がなぜ生まれ、なぜ30年間も解決されないのか。
本記事では、SI営業の技術者依存が根深い構造的問題となった歴史的経緯と、その解決への道筋を詳しく分析します。
こんな状況に心当たりはありませんか?
SI営業の現場では、次のような声が日常的に聞かれます。これらは偶然の出来事ではなく、SI業界が抱える構造的な問題の典型的な症状なのです。
「山田PM(プロジェクトマネージャー)が定年退職してから、あの案件の全体像が分からなくなった...」
「優秀だった田中さんが異動して3年経つのに、なぜかその顧客との契約だけは続いている」
「昔は凄腕のSEがいて大きな案件を取ったらしいが、今は誰も技術的な話ができない」
SIer営業の技術者依存が根深い3つの歴史的要因
SI営業の技術者依存は、複数の歴史的要因が複雑に絡み合って生まれた構造的問題です。ここでは、その中でも特に重要な3つの要因を詳しく見ていきます。
1. 優秀な技術者による案件受注と人材異動による「技術の空洞化」
SI業界の最も根深い問題は、優秀な技術者が受注した案件が長期契約として継続する中で、当初の技術者が異動・退職し、技術的な理解が組織から失われていく構造にあります。
なぜ長期契約になりやすいのか?
SI案件の多くは、サーバやパソコンなどのハードウェアの保守可能期間(通常5〜10年)に依存します。システムのライフサイクルが長期にわたるため、必然的に契約も長期化します。さらに、顧客側でも担当者が数年で異動し、システムの詳細を把握している人がいなくなることで、「現状維持が最も安全」という判断に傾きがちです。
典型的な技術空洞化のプロセス
フェーズ1:優秀な技術者による受注(1990年代〜2000年代)
高いスキルを持つSEやPM(プロジェクトマネージャー)が顧客の複雑な要件を理解し、技術的な深い議論を通じて大型案件を受注します。顧客からの信頼も厚く、長期契約へと発展していきます。
フェーズ2:人材流動と暗黙知の散逸(2000年代〜2010年代)
優秀な技術者の昇進、異動、転職、退職により、技術的な背景や設計思想が後任に十分に引き継がれません。「なぜこの設計にしたのか」「どこが重要なポイントなのか」といった暗黙知が属人化したまま失われていきます。
フェーズ3:契約慣性と技術理解の低下(2010年代〜現在)
顧客側も担当者が変わり、当初の技術的経緯を知る人がいなくなります。
しかし契約は継続し、保守・運用・小改修が発生。営業は技術的な背景を理解できず、PM(プロジェクトマネージャー)やプリセールスに完全依存する状況に陥ります。
この構造の問題点:
受注時は優秀な技術者が深い技術議論を通じて顧客との信頼関係を構築し、大型案件を受注します。
しかし5〜10年後、人材異動により技術理解のない営業が引き継ぐと、「後日技術者から連絡します」という対応しかできず、PM(プロジェクトマネージャー)・プリセールス依存の御用聞き営業に転落してしまうのです。
2. 1990年代バブル崩壊による「IT丸投げ文化」の定着
日本のIT業界における技術者依存構造は、1991年のバブル崩壊という経済的転換点から始まりました。この時期の企業の判断が、現在まで続く構造的問題の土台を作ることになったのです。
バブル崩壊前後の大転換
| 時期 | 状況 |
|---|---|
| バブル崩壊前(1980年代) |
・大手企業は自社で大規模なSE部門を保有 ・情報システム部門が企業の重要な競争力源泉 ・発注者側にも技術を理解する担当者が存在 |
| バブル崩壊後(1990年代) |
・膨大なSEを抱える人件費が経営を圧迫 ・「ITは専門会社に丸投げしよう」という経営判断の急増 ・発注者側の技術理解も外部委託により希薄化 |
SIer営業への決定的影響
この時期に確立された「IT丸投げ文化」により、発注者側も受注者側も「技術的なことは専門家に任せるのが当然」という意識が定着しました。
30年後の現在への影響:
- 発注者:「技術的なことはよく分からないが、お任せします」
- SIer営業:「技術的なことはPM(プロジェクトマネージャー)から後日ご連絡します」
- 双方の技術理解不足により、本質的な価値議論が困難
3. 長期契約の慣性による「現状維持の罠」
SI業界では、一度受注した案件が10年、15年と続くことは珍しくありません。この長期契約の慣性こそが、技術者依存を固定化する最も強力な要因となっています。
長期契約慣性のメカニズム
ハードウェア保守期間に起因する契約継続
サーバ・ネットワーク機器の保守期間(5〜7年)、PC・周辺機器の更新サイクル(3〜5年)に合わせて、保守契約が自動更新される仕組みが定着しています。
顧客側の担当者変更による判断回避
3〜5年での人事異動サイクルにより、新任担当者は「前任者の判断を踏襲」することが最も安全な選択となります。システムの詳細を把握する時間もモチベーションもない状況が続きます。
技術的参入障壁の高さ
既存システムの技術的背景を理解するのに膨大な時間がかかり、競合他社が参入するには高すぎる学習コストが発生します。結果として「切り替えるメリット < 切り替えるリスク」の状況が継続します。
現状維持の罠の実態
受注時(過去)
優秀な技術者Aが深い技術議論を通じて大型案件を受注します。顧客との信頼関係も厚く、長期的なパートナーシップが始まります。
5年後
技術者Aが異動し、技術者Bが対応を引き継ぎますが、この時点で顧客担当者も異動しており、新担当者は現状維持を選択します。システムの詳細を把握する時間もなく、「前任者の判断を踏襲」することが最も安全な選択となります。
10年後
技術者Bも退職し、プロジェクトマネージャーCが表面的な対応のみを行う状況になります。顧客側も2代目担当者となり、さらに実態把握が困難になっています。
15年後(現在)
プロジェクトマネージャーCも異動し、営業が困惑する中、顧客側も3代目となり、もはや誰も全体像を把握していない状況で「とりあえず継続」という判断が下されるのです。
4. 人月商売とITゼネコン構造による営業価値の矮小化
日本のSI業界を特徴づける「人月商売」と「ITゼネコン構造」。これらの仕組みが、営業の技術理解を不要なものとして制度化し、30年間にわたって営業の価値を矮小化してきました。
人月商売による営業価値の矮小化
- システムの価値ではなく「何人月で作るか」が価格決定要因
- 営業の役割が「人の調達と価格交渉」に限定
- 「技術的価値創出はエンジニア、商談は営業」という分業の固定化
ITゼネコン構造の問題
元請けの大手SIerは営業とPM(プロジェクトマネージャー)が中心となり、基本設計や詳細設計を二次請けの中堅SIerに委託します。さらに二次請けは実装を三次請けの小規模SIerに委託するという、建設業界のゼネコンに似た多重下請け構造が形成されています。
この構造下では、元請けSIerの営業は「技術的なことは下請けに任せれば解決する」という発想に陥りがちです。技術的な詳細を理解しなくても、下請け企業が実装してくれるため、営業自身が技術を学ぶ必要性を感じなくなってしまうのです。
30年間継続する悪循環
まず、優秀な技術者が案件を受注し、それが長期契約化します。その後、技術者が異動すると営業が引き継ぎますが、営業は技術を理解せずとも契約慣性により継続できてしまいます。これにより技術理解の必要性を感じなくなり、さらに技術から距離を置くようになります。そして新規案件でも「技術は専門家任せ」という姿勢が当たり前となり、依存体質が組織全体に拡大していくのです。
なぜ30年間も解決されないのか?慣性に支配された構造的阻害要因
これまで見てきた歴史的要因により生まれた技術者依存体質。なぜこの問題は30年間も解決されないのでしょうか。そこには、慣性に支配された3つの構造的な阻害要因が存在します。
契約継続による「技術理解不要」の成功体験
最も根深い問題は、技術を理解していない営業でも契約が継続してしまうという皮肉な成功体験にあります。
慣性による成功体験の罠
- 過去の優秀な技術者の貯金で契約が自動継続
- 「技術が分からなくても売上は上がる」という錯覚
- 短期的には問題が表面化しないため、改革の必要性を感じない
具体的な現場の実態
営業A:「技術は全然分からないけど、毎年1億円の契約更新できてる」
営業B:「PM(プロジェクトマネージャー)の山田さんがいれば何とかなる」
営業C:「お客さんも技術的なことは求めてないし...」
この成功体験により、営業は技術学習へのインセンティブを完全に失い、現状維持バイアスが強化されます。
技術者異動による知識継承の断絶
SI業界は人材の流動性が高く、これが技術知識の組織的継承を阻害する大きな要因となっています。
知識継承断絶の3つのパターン
| パターン | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 優秀な技術者の昇進・異動 |
案件を熟知した技術者が管理職に昇進 現場を離れ、詳細な技術知識が失われる |
後任者は表面的な対応しかできない |
| 技術者の転職・退職 |
SI業界の厳しい労働環境による人材流出 退職時の引き継ぎが不十分 |
暗黙知(なぜそうしたか)が完全に失われる |
| 組織再編による担当変更 |
部門統合や組織変更による担当替え 案件の歴史的経緯が引き継がれない |
新担当者は「とりあえず現状維持」を選択 |
この結果、技術者が異動すると知識が断絶し、営業は困惑してPM(プロジェクトマネージャー)に依存し、さらに技術から距離を置くという悪循環が生まれるのです。
既得権益化した役割分担の固定化
30年間にわたって固定化された役割分担は、もはや各部門の既得権益となり、変革を阻む最大の障壁となっています。
部門別既得権益の構造
PM(プロジェクトマネージャー)・プリセールス部門
- 営業の技術理解向上 = 自部門の影響力削減
- 「技術的なことは我々の専門領域」という既得権の維持
- 営業の技術力向上に対する潜在的な抵抗
営業部門
- 技術学習 = 追加の負担・責任
- 「今のやり方で問題ない」という現状維持の合理化
- 技術理解を求められることへの心理的抵抗
経営層
- 短期的な売上に問題がなければ改革の必要性を感じない
- 部門間対立を避けたい心理
- 構造改革のコストとリスクを回避
真の構造改革は既得権益の再配分を伴うため、各部門が保身のために改革に抵抗する構造が生まれています。この組織政治により、30年間本質的な改革が先送りされ続けているのです。
変革を成功させるための重要な視点
30年間続いた構造問題を変革するには、精神論ではなく具体的な行動と仕組みが必要です。ここでは、実際に変革に成功した企業の事例から導き出された、2つの重要な視点を紹介します。
経営トップ自らが技術の重要性を体現する
変革の成否を分けるのは、経営層の本気度です。「技術を理解しよう」と号令をかけるだけでは組織は動きません。経営トップ自身が技術を学び、その姿勢を組織全体に示すことが不可欠です。
経営会議の議題に「技術理解度向上の進捗」を必ず入れ、各部門長に具体的な数値目標と達成状況を報告させることも重要です。ある大手SIerでは、「営業の技術資格取得率」「技術提案の採用率」「PM(プロジェクトマネージャー)同行なしの商談実施率」を経営指標として設定し、四半期ごとに進捗を確認しています。
さらに効果的なのは、昇進要件を変更することです。富士通では、課長以上の昇進要件に「基本情報技術者試験合格」または「自社技術認定資格の取得」を必須条件として追加。これにより、営業部門全体に「技術を理解しないと昇進できない」という明確なメッセージが伝わりました。
小さな成功事例を組織全体で共有し、横展開する
大規模な組織改革を一気に進めようとすると、必ず抵抗勢力が生まれます。まず小さなパイロットチームで成功事例を作り、その成果を組織全体に広げていく方法が効果的です。
重要なのは、成功事例を「特別な人だからできた」ではなく「普通の営業でもできる」ストーリーとして伝えることです。資料には具体的な学習方法、つまずいたポイント、それをどう乗り越えたかを詳細に記載し、追随する営業が同じ道を辿れるようにすることが大切です。
変革は決して簡単ではありませんが、これらの具体的な取り組みを着実に実行することで、30年間の慣性を断ち切ることは可能です。重要なのは、抽象的な理想論ではなく、明日から実行できる具体的なアクションを積み重ねることなのです。
まとめ:歴史を理解し、未来を創造する
SIer営業の技術者依存は、1990年代バブル崩壊から始まった30年間の歴史的構造問題です。
サーバやパソコンの保守期間に起因する長期契約、顧客側の担当者変更、人月商売とITゼネコン構造など、複数の要因が絡み合って生まれた根深い問題です。
しかし、歴史を理解することは、未来を変える第一歩です。デジタル時代の到来により、従来の「技術は専門家任せ」モデルは限界を迎えています。
今こそ必要なのは:
- 30年間の慣性を断ち切る勇気
- 段階的でも着実な改革の実行
- 技術とビジネスを統合した新しい営業像の構築
変革は決して容易ではありませんが、歴史を学び、構造を理解し、現状の紐解きからはじめ具体的な一歩を踏み出しましょう。
この記事を書いた人
|
openpage 事業開発部長 北森雅雄(kitamori masao) NTT東日本で14年間、自治体SE、新規事業開発、デジタルマーケティングを経験し、総額10億円の案件創出や年間ARR10億円規模の事業立ち上げを実現。2025年にopenpageに転職し、現在は事業開発部長として8がけ社会時代の営業DX推進に取り組む。 |
 |
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら