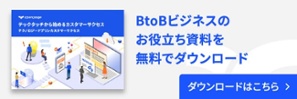松下洸平と見上愛が出演する朝日新聞社のショートドラマ「新しい朝をつくれ。」の「8がけ社会編」を視聴し、地方自治体での営業経験を持つ筆者の視点から考察します。このドラマは単なる企業プロモーション映像を超えて、現代ジャーナリズムの本質と地方が抱える課題を巧妙に描いた作品として注目に値します。
「8がけ社会」についての解説も別記事で掲載しておりますので、あわせてご覧ください。
視聴してまず感じたリアリティ
松下洸平のナレーションで始まるこのショートドラマを視聴して、まず印象的だったのは、その「リアルさ」でした。見上愛演じる春田あやめ記者の動きや表情、商店街での自然な会話など、作り込まれた感じがしない自然体の演出が印象的です。
特に、コロッケを買う場面での「お姉さん食べる前から嬉しそうな顔してる」「コロッケ1個おまけしちゃう」というやり取りは、地方取材の現場でよく見る光景そのものでした。このような何気ない日常の一コマから、記者と地域の人々との関係性が自然に描かれている点に、制作陣の現場理解の深さを感じました。
自身の地方営業体験と重なる記者の姿
私がNTT東日本で自治体向けシステム提案をしていた頃の体験と、春田記者の取材スタイルに多くの共通点を見つけました。地方での営業活動と記者の取材活動は、実は非常に似通った部分があります。
商店街での偶然の出会いが生む本音
私が地方の自治体を訪れる際、必ずといっていいほど商店街を通り抜けました。10年前でさえ、シャッターが下りた店舗が目立ち、残っている店の店主の方々は皆さん高齢でした。
ある時、とある自治体の担当者との打ち合わせ後、駅前の商店街を歩いていると、まさにドラマと同じように「お兄さん、どちらから来たの?」と声をかけられたことがあります。東京から来たと答えると、「最近は若い人が全然いなくてね」と寂しそうに話されたのを覚えています。
当事者意識を持つ記者の複雑な立場
動画で印象的だったのは、春田記者が「うちも結構人減ってますね」と答える時の表情でした。少し困ったような、でもどこか親近感のある表情。これは取材対象と同じ立場に立っているからこその反応だと感じました。
私も自治体の方々と話す時、「我々も同じ課題を抱えている」という共感から始まる会話が多かったことを思い出します。この共感が、相手の本音を引き出す重要な要素になることを、営業を通じて実感していました。
中江和仁監督の巧みな演出技法
このドラマの監督を務めた中江和仁氏は、「きのう何食べた?」「大豆田とわ子と三人の元夫」などの話題作を手がけてきた実力派です。今回の「8がけ社会編」でも、その演出力が存分に発揮されています。
日常の延長線上で社会問題を描く手法
中江和仁監督 中江和仁 - Wikipediaの過去作を見ても分かるように、監督は重いテーマを日常の延長線上で描くのが非常に巧みです。
今回の「8がけ社会編」でも、コロッケを買うという何気ない日常から始まり、自然に人口減少問題へと話題を移していく構成は見事でした。視聴者が身構えることなく、社会問題に向き合える導線を作っている点は、さすがの演出力だと感じました。
飛び込み取材の重要性を描写
動画では「春田の取材スタイルは飛び込み取材も好きです」というナレーションがありました。これは現代のジャーナリズムにおいて重要な要素だと思います。
私が自治体との商談で感じたのは、「アポイントを取った正式な会議」では出てこない本音が、廊下での立ち話や、偶然の出会いから生まれることが多いということでした。春田記者の飛び込み取材への親和性は、まさに現場の真実を掴むために必要なスキルを表現していると感じました。
地方出身記者が抱える複雑なアイデンティティ
春田記者の設定で最も興味深いのは、彼女自身が地方出身でありながら、現在は東京の本社で働いているという立場です。この複雑なポジションが、ドラマに深みを与えています。
当事者と観察者の微妙な境界線
「私は北海道です。札幌から1時間半くらいのところで、あ、結構田舎で」という春田の自己紹介は、非常に興味深い表現でした。地方出身でありながら、今は東京の本社にいる。取材対象と同じ境遇でありながら、記者として客観的に報じなければならない。
この複雑な立場は、私自身も営業活動で経験しました。地方の自治体を訪問する際、東京の本社から来た営業として接されながらも、父の故郷を思い出すと同じような課題を肌で感じている。この微妙なポジションが、相手との距離感を絶妙に調整してくれることがありました。
一言に込められた深い共感
「うちも結構人減ってますね」という春田記者のこの一言に込められた想いは深いと感じました。単なる同情ではなく、自分の故郷も同じ問題を抱えているという当事者としての実感。記者としての客観性を保ちながらも、完全に他人事にはできない複雑さが見事に表現されています。
ジャーナリズムの原点を問い直す回想シーン
ドラマの中で最も印象的だったのは、春田記者が記者を志した原点を振り返る回想シーンでした。この場面は、現代ジャーナリズムの本質的な価値を問い直すメッセージが込められています。
地方メディアが持つ特別な意味
「高校生の頃、新聞に地元のお祭りが取り上げられたことを自分たちの町やそこで過ごした日々を誇らしく思えた」
この回想シーンを見て、私は自分が初めて地方自治体の広報誌に掲載された時のことを思い出しました。小さなプロジェクトでしたが、地元の人たちに「新聞に出てたね」と声をかけられた時の嬉しさは今でも覚えています。
メディアが地方に与える影響の大きさ、そして地方の人々がメディアに求めているものの本質を、この短いシーンで見事に表現していると感じました。全国ニュースにはならないような小さな出来事でも、地域の人々にとっては大切な誇りの源泉になるのです。
「誰かの輝く瞬間を記事にしたい」という純粋な動機
春田記者が抱く「誰かの輝く瞬間を記事にしたい」という想いは、ジャーナリズムの最も純粋な動機を表現しています。これは大きなスクープを追うことだけがジャーナリズムではないという、重要なメッセージでもあります。
企業ブランディングとしての完成度
このドラマは朝日新聞社のブランディング施策の一環として制作されましたが、その完成度の高さに驚かされます。単なる企業PRを超えた作品として成立している点が素晴らしいです。
宣伝臭さを感じさせない自然な構成
このドラマを見て感心したのは、朝日新聞の宣伝臭さを全く感じさせないことでした。むしろ、ジャーナリズムの本質的な価値について考えさせられる内容になっています。
制作にあたり若手記者にヒアリングした際のエピソードをもとに構成しました 松下洸平さん、見上愛さんが朝日新聞社の記者を演じるショートドラマ「新しい朝をつくれ。」第2話を公開 | 株式会社朝日新聞社のプレスリリースとあるように、実際の記者の体験に基づいているからこその説得力があります。
現代的なメディア戦略の反映
動画内では直接触れられていませんが、人気コンテンツである『朝日新聞ポッドキャスト』で、記事では書ききれなかったことも伝えようとする様子も 松下洸平、見上愛が朝日新聞社の記者を熱演!朝日新聞社ショートドラマ&コーポレートCM公開描かれているという設定は、現代のメディア戦略を反映しています。
私がデジタルマーケティングを担当していた時期、「一つのコンテンツを複数のチャネルでどう展開するか」は常に課題でした。朝日新聞のこの取り組みは、その成功事例の一つといえるでしょう。
8がけ社会というテーマの深層
このドラマが扱う「8がけ社会」というテーマは、単なる人口統計の問題ではありません。一人ひとりの人生に直結する複雑な課題を、個人のストーリーを通じて描いている点が秀逸です。
統計を人間ドラマに昇華させる手法
動画を通して強く感じたのは、8がけ社会という大きな社会問題を、個人のストーリーに落とし込む巧みさでした。春田記者の個人的な体験と記者としての使命感、そして取材対象との関係性が重層的に描かれています。
私自身、自治体の人口減少問題に向き合う中で、それが単なる統計数字ではなく、一人ひとりの人生に直結する問題だということを痛感していました。このドラマはその複雑さを短時間で見事に表現していると思います。
制作陣の現場理解の深さを感じる完成度
このショートドラマを視聴して、制作陣の「現場への理解」の深さを強く感じました。単なる社会問題の啓発動画ではなく、地方取材の現場で実際に起こりうるリアルな人間ドラマとして成立しています。
記者という職業の持つ矛盾や複雑さ、そして地方と都市部の微妙な関係性を、押し付けがましくなく描いている点は、中江和仁監督の演出力の高さを物語っています。
特に印象的だったのは、最後のナレーション「これは人口減少の未来に挑戦するためにどうしていくべきか。新たな可能性を探そうとする記者たちの物語」という部分です。問題提起で終わるのではなく、「新たな可能性を探す」という前向きなメッセージで締めくくっているところに、朝日新聞社の姿勢が表れていると感じました。
このドラマは、8がけ社会という社会問題を扱いながら、同時にジャーナリズムの本質的な価値について考えさせる、完成度の高い作品だったと思います。
この記事を書いた人
|
openpage 事業開発部長 北森雅雄(kitamori masao) NTT東日本で14年間、自治体SE、新規事業開発、デジタルマーケティングを経験し、総額10億円の案件創出や年間ARR10億円規模の事業立ち上げを実現。2025年にopenpageに転職し、現在は事業開発部長として8がけ社会時代の営業DX推進に取り組む。 |
 |
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら