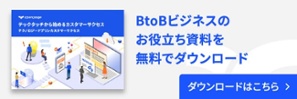そもそも「8がけ社会」って何?
2024年、ある造語が日本のビジネス界で急速に広まりました。それが「8がけ社会」です。
「8がけ社会」に関するショートドラマの感想も別の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
8がけ社会とは?
この言葉は、2040年に予測される深刻な労働力不足を表現したものです。日本の労働力人口が現在より約2割(1,200万人)減少することから、「2割減 = 8がけ」という分かりやすい表現が生まれました。メディア企画から始まったこの概念は、現在では大手企業の経営戦略文書にも使用されるほど浸透しています。
- 2040年に日本の労働力人口が現在より約2割(1,200万人)減少
- 「2割減 = 8がけ」という分かりやすい表現
- メディア企画から始まり、今では大手企業も経営戦略で使用
なぜこの言葉がこれほど注目されるのでしょうか?答えは「具体性」にあります。
「少子高齢化が進んでいます」と言われても、経営者にとってはどこか他人事でした。しかし「2040年に労働力が2割減る」と聞くと、話は別です。あと16年という現実的な時間軸で、明確な数字が示されているからです。
営業現場では既に深刻な人手不足が始まっている
特に営業組織での影響は深刻です。現在でも「良い営業人材が採れない」という声をよく聞きますが、データを見ると状況の深刻さがわかります。
営業職の人材確保の現状
営業職の人材確保は他の職種と比べて特に困難な状況にあります。リクルートの調査データを見ると、営業職の有効求人倍率は全職種平均を大きく上回っており、企業が求める営業人材と実際の求職者数に大きなギャップが生じていることがわかります。
- 営業職の有効求人倍率:2.09倍
- 全職種平均:1.27倍
- つまり営業職は他の職種より約1.6倍も人材確保が困難
この状況が16年後にはさらに深刻化するのは確実です。
当初の解決策:「とにかく人を増やそう」
8がけ社会への対応策として、多くの企業が最初に考えたのは人材確保の強化でした。
従来のアプローチ(人を増やす発想)
8がけ社会の課題が注目され始めた当初、多くの企業や専門家が提案したのは「労働力の量的拡大」による解決策でした。これは従来の人手不足対策の延長線上にある発想で、不足する労働力を外部から補充することで問題を解決しようとするものです。
- 外国人労働者の積極採用
- 高齢者雇用の拡大
- 女性活躍推進による労働参加率向上
- 採用活動の強化・多様化
確かにこれらは一定の効果をもたらします。しかし根本的な問題があります。
この発想は結局「同じ仕事を同じやり方で、ただ人数を増やして対応する」という従来の延長線上にあるからです。しかし8がけ社会の本質的な課題は、そもそも「同じやり方」が通用しなくなることなのです。
大転換:「働き方そのものを変える」という発想
そこで生まれた新たな認識がこれです。
「人手不足はこれまでの常識を見つめ直す機会になる」
新しいアプローチ(働き方を変える発想)
この考え方の転換により、解決策の軸が大きく変化しました。単純に労働力を増やすのではなく、既存の労働力でより大きな成果を生み出す「質的変革」にフォーカスが移ったのです。この変化は、日本の労働環境における根本的なパラダイムシフトを意味します。
- 人数を増やすのではなく、一人ひとりの生産性を向上
- 同じ人数でより大きな成果を生み出す組織への変革
- 量的解決から質的変革への転換
営業現場で起きている意識変化の実例
この文脈変化は、営業組織の現場でも顕著に現れています。
相談内容の変化
実際に企業から受ける相談内容を比較してみると、明らかな変化が見られます。従来は「人員増」による解決を前提とした相談が主流でしたが、現在では「既存リソースの最大化」を前提とした相談が増えています。この変化は、企業の意識が根本的に変わってきていることを示しています。
5年前の相談例 「今期の目標達成のために営業を3名増員したいのですが...」
最近の相談例
「現在の営業チームで売上を1.5倍にするにはどうすればいいでしょうか?」
ベテラン退職時の対応変化
ベテラン営業パーソンの退職への対応も大きく変わっています。以前は「代替人材の確保」が最優先でしたが、現在では「知識・経験の組織化」に重点が置かれるようになりました。これは個人に依存した営業スタイルから、組織的な営業力への転換を意味します。
従来の発想 「同レベルの経験者を採用しなければ」
現在の発想 「このベテランのノウハウをチーム全体で活用できるようにするには?」
実際、先日も大手製造業の営業部長からこんな相談を受けました。
「エース営業が来月退職するのですが、その人が築いてきた顧客との関係性や提案ノウハウを、どうすれば組織の資産として残せるでしょうか」
5年前なら「後任者の採用」の話が中心だったことを考えると、明らかに企業の意識が変わってきています。
鍵となる「暗黙知」の「形式知」化
営業は特に属人性が高い仕事です。優秀な営業パーソンは多くのスキルを感覚的に身につけていますが、これらが個人の「暗黙知」として蓄積されている限り、組織全体の資産にはなりません。
8がけ社会で求められる取り組み
8がけ社会を乗り切るためには、個人に蓄積された「暗黙知」を組織で共有できる「形式知」に変換することが不可欠です。これは単なる情報共有ではなく、優秀な営業パーソンの思考プロセスや判断基準を体系化し、再現可能な形にすることを意味します。
- 成功事例の体系化:なぜその商談が成功したのかを詳細に分析
- 提案プロセスの標準化:再現可能な形でのノウハウ共有
- 顧客対応パターンの蓄積:状況別の最適な対応方法をデータベース化
これにより、経験の浅い営業でもベテランレベルの提案ができるようになります。
デジタル技術が実現する営業変革
従来の営業活動では、こんな曖昧な判断が当たり前でした。
- 「あのお客様は興味を持っていそうでした」
- 「提案に前向きな印象を受けました」
可視化できるデータ例
デジタルセールスルーム「openpage」のようなツールを活用すると、従来は営業パーソンの感覚に頼っていた顧客の反応や関心度を、具体的な数値として把握できるようになります。これにより、営業活動の精度が劇的に向上し、成功要因の分析も客観的に行えるようになります。
- どの資料にどれくらいの時間をかけて見ているか
- どの部分に最も関心を示しているか
- 何度資料を確認しているか
顧客のエンゲージメントを具体的な数値として把握できるようになり、成功した商談のプロセスを詳細に記録・分析することで、「なぜその商談が成功したのか」を客観的に理解できます。
その成功パターンを他の商談にも応用できれば、個人の経験や勘に頼った従来の営業スタイルから大きく転換できます。
今すぐ始めるべき準備
8がけ社会の到来まで残り16年。この期間を「準備期間」として活用できるかどうかが、営業組織の未来を左右するでしょう。
重要なのは、8がけ社会を「脅威」ではなく「変革の機会」として捉えることです。人手不足という制約があるからこそ、これまで当たり前だった業務プロセスを根本から見直し、より効率的で持続可能な営業スタイルを構築するチャンスが生まれています。
この変革に成功した営業組織が、2040年の8がけ社会でも競争優位を維持し続けるでしょう。変化を先取りして準備を始める企業こそが、次の時代の勝者となります。
そして、その準備は「明日から」ではなく「今日から」始める必要があります。
この記事を書いた人
|
openpage 事業開発部長 北森雅雄(kitamori masao) NTT東日本で14年間、自治体SE、新規事業開発、デジタルマーケティングを経験し、総額10億円の案件創出や年間ARR10億円規模の事業立ち上げを実現。2025年にopenpageに転職し、現在は事業開発部長として8がけ社会時代の営業DX推進に取り組む。 |
 |
大手企業から中小企業・地方企業にも選ばれているデジタルセールスルーム:openpageの資料ダウンロードはこちら